共通教育センター
学生のためのブックガイド2009
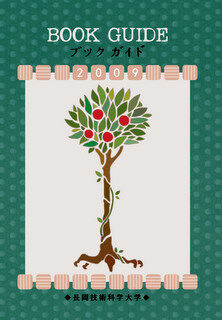
この本は、教員による推薦書紹介であるだけでなく、学生との読書をめぐる対話集であるとも言えます。執筆者は学生に自身の読書体験を告白しています。
この本を読みすすめると、執筆者が学生時代にあるいは、執筆者が進路を決定しようと模索していた時に、出会った本の逸話が語られています。人によっては、一冊の本、ある作家との出会いによって、大きくその後の人生を変化させることもあるでしょう。
読書という想像力の旅は、私たちの心にある種のウィルスのように侵入して、その後の想像力の旅を支配するかもしれません。このブックガイドを利用して、本を探し、更に読書経験を積み重ねるということも大切な時間です。
また、このブックガイド自体の読書を楽しむことも可能かと考えます。いずれにせよ、このブックガイドが、本学教員と学生との読書をめぐる対話となることを願ってやみません。
ブックガイド目次
自然・工学編
- 1.「科学・技術の美しさを追い求めて」小野浩司(1、2ページ)
- 2.「研究の心構え」綿引 宣道(3〜5ページ)
- 3.「日本の工学の父、山尾庸三のこと」三上 喜貴(6〜8ページ)
- 4.「憧れ」永森 正仁(9〜11ページ)
- 5.「なぜ人間は五つの大陸で異なる発展をとげたのか?」中出 文平(12、13ページ)
- 6.「いつかこの手で大聖堂を建てたい」中出 文平(14、15ページ)
- 7.「ここで終わりにしたいと思います」中出 文平(16、17ページ)
- 8.「実験や進路で悩んだときの教科書」高橋 祥司(18、19ページ)
- 9.「オランダで土木技術の英知に触れる」田中 泰司(20、21ページ)
- 10.「企業で指導的技術者になる皆さんへ」南口 誠(22、23ページ)
- 11.「1年前の私は今の私ではない」丸山 久一(24〜26ページ)
- 12.「再び数学とは何か」小林 曻治(27〜29ページ)
- 13.「量子化学計算のすすめ」村上 能規(30ページ)
- 14.「現代を生きる恐竜」高原 美規(31、32ページ)
- 15.「無駄とは何だろうか?~「無駄学」入門~」三宅 仁(33、34ページ)
- 16.「「明らか」が「明らか」なわけは?」北谷 英嗣(35〜37ページ)
- 17.「身の回りの化学発光」村上 能規(38ページ)
- 18.「技術革新は、地球規模の問題を解決する!?」松丸 幸司(39、40ページ)
- 19.「雷の日にコーヒーを飲むときは?―雷から身を守るには」鈴木 泉(41〜43ページ)
- 20.「技術科学を志す学生諸君へ」中川 匡弘(44ページ)
- 21.「積を和に 対数の発見物語」中川 健治(45、46ページ)
- 22.「十年経っても古くならないコンピュータの本」湯川 高志(47、48ページ)
- 23.「誰が何と言おうとも、僕はわかった」下村 匠(49、50ページ)
- 24.「はやい、うまい、やすい」黒木 雄一郎(51、52ページ)
- 25.「少しでいいから分けてよその賞金!」原 信一郎(53、54ページ)
- 26.「一流の科学者には筆の立つ人が多い」丸山 一典(55〜59ページ)
社会・人文編
- 27.「「深夜特急」へのあこがれ」田浦 裕生(60、61ページ)
- 28.「あなたの時間を数倍に増やす魔法の方法」三木 徹(62〜64ページ)
- 29.「名著との出会い」淺井 達雄(65〜67ページ)
- 30.「異界の旅」高橋 秀雄(68、69ページ)
- 31.「誰もが悪と無縁ではない」細山田 得三(70、71ページ)
- 32.「日本古代史 先ずは、建国の物語を知る。議論はそれから。」内田 希(72、73ページ)
- 33.「日本人論として」内田 希(74、75ページ)
- 34.「源氏物語創作一千年紀に本学学生諸君に読ませたい本」福本 一朗(76〜78ページ)
- 35.「リズムに乗って元気を出そう」丸山 久一(79〜81ページ)
- 36.「小説の効能」安原 明子(82〜85ページ)
- 37.「自壊する帝国と資本主義」村上 直久(86〜89ページ)
- 38.「ウチとソトの境界を愉しむ」松田 真希子(90〜92ページ)
- 39.「凡事徹底」姫野 修司(93、94ページ)
- 40.「物語の愉しみ」木村 悟隆(95、96ページ)
- 41.「大人の伝記」斎藤 秀俊(97、99ページ)
- 42.「「音」への誘い」加納 満(100、101ページ)
- 43.「知のあり方を考えさせてくれたある哲学者のメッセージ」中村 和男(102、103ページ)
- 44.「「方法論」の存在に気付かされた」武井 由智(104〜106ページ)
- 45.「野性の実践」高橋 綾子(107、108ページ)
