細胞が動くしくみを観て理解する研究の魅力と未来 – 藤原 郁子

物質生物系 准教授 藤原 郁子
Q. 研究の目的について教えてください。
細胞には形を保つための「骨」のような構造があります。これは単なる支えではなく、細胞が動くためのエンジンのような役割も果たします。しかし、その仕組みはまだ完全には解明されていません。私達の研究室では、この細胞の動きを生み出す仕組みを研究し、がん細胞の運動や細胞の修復メカニズムの解明、さらには自走マイクロマシンの開発などにつなげたいと考えています。
Q. 細胞の動きを支える仕組みがあるんですね!どのような方法で研究しているのですか?
TIRF顕微鏡という特殊な光学顕微鏡を使っています。この顕微鏡は、光を全反射させた際に反対側に生じるわずかな光を利用して試料を照らすため、通常の顕微鏡では見えない、反射面から約100nmという狭い領域の現象のみを鮮明に観察できるのが特徴です。この技術を用いることで、アクチンがファイバー構造を作っていくようなダイナミックな変化をリアルタイムで捉えることができます。
Q. アクチンとMreBの研究を進めることで、どのようなことがわかるのでしょうか?
アクチンは真核細胞に、MreBは細菌といったように全く違う生物に存在するタンパク質ですが、両者には多くの共通点があります。私たちを含め最近の研究から、MreBは細菌の形や細胞壁を保つだけでなく、実は運動にも関わっていることが示されつつあります。つまり、生き物の種類が違っても、細胞レベルでは似た仕組みで動いている可能性があるのです。この仕組みは、遥か昔の原始的な細胞から受け継がれてきた重要な機能だと考えられており、最近、注目されています。
Q. 研究を通じて高校生に伝えたいことはありますか?
科学では、何となく「知っているつもり」になっていることを掘り下げることで、まったく新しい発見につながることがあります。例えば、アクチンは長年研究されていますが、まだ謎が多く残っています。「なぜこうなるのだろう?」という疑問を持ち続けることが、新しい発見の第一歩です。
Q. 身近なことでも、深く考えれば新しい発見があるかもしれませんね!
その通りです。科学は、教科書の知識を覚えるだけでなく、未知の世界を探る面白さがあります。ぜひ、自分の興味を大切にして、自由に考え、探求する楽しさを味わってほしいです。

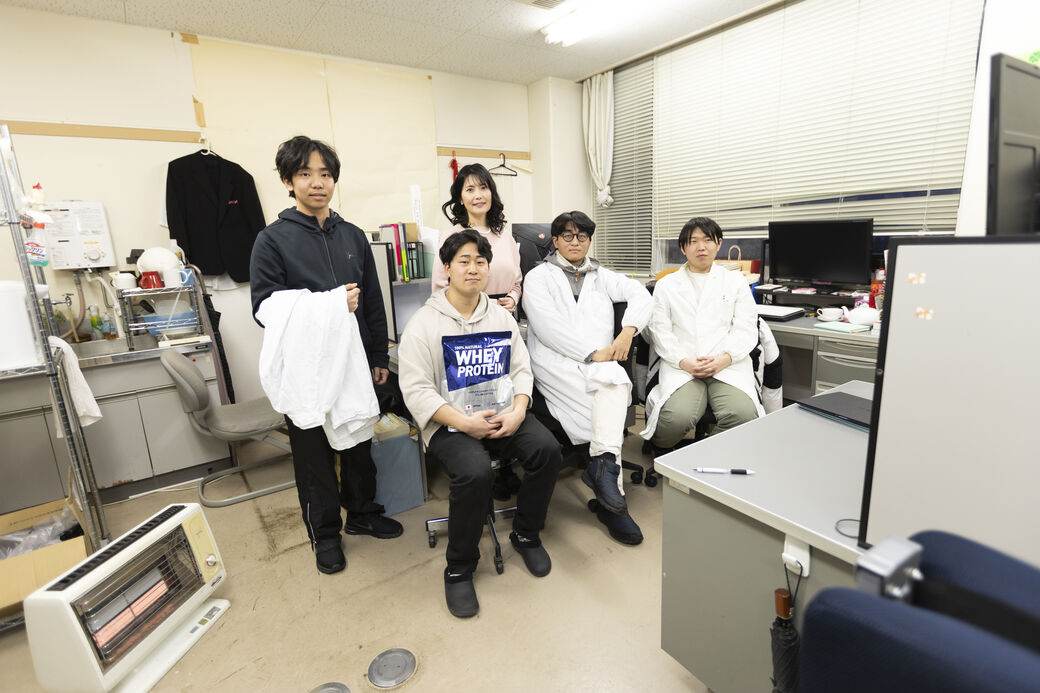
藤原 郁子 Fujiwara Ikuko
物質生物系 准教授(2025年4月現在)
- 2022年4月 - 現在 長岡技術科学大学 物質生物系 准教授
- 2021年4月 - 2022年3月 長岡技術科学大学 生物機能工学専攻 准教授
- 2019年4月 - 2021年3月 大阪市立大学 生物地球系専攻 助教
- 2015年1月 - 2019年3月 名古屋工業大学 特任助教
- 2014年4月 - 2014年12月 京都大学 助教
- 2006年9月 - 2014年3月 米国立衛生研究所 研究員
- 2004年8月 - 2006年9月 エール大学 研究員

