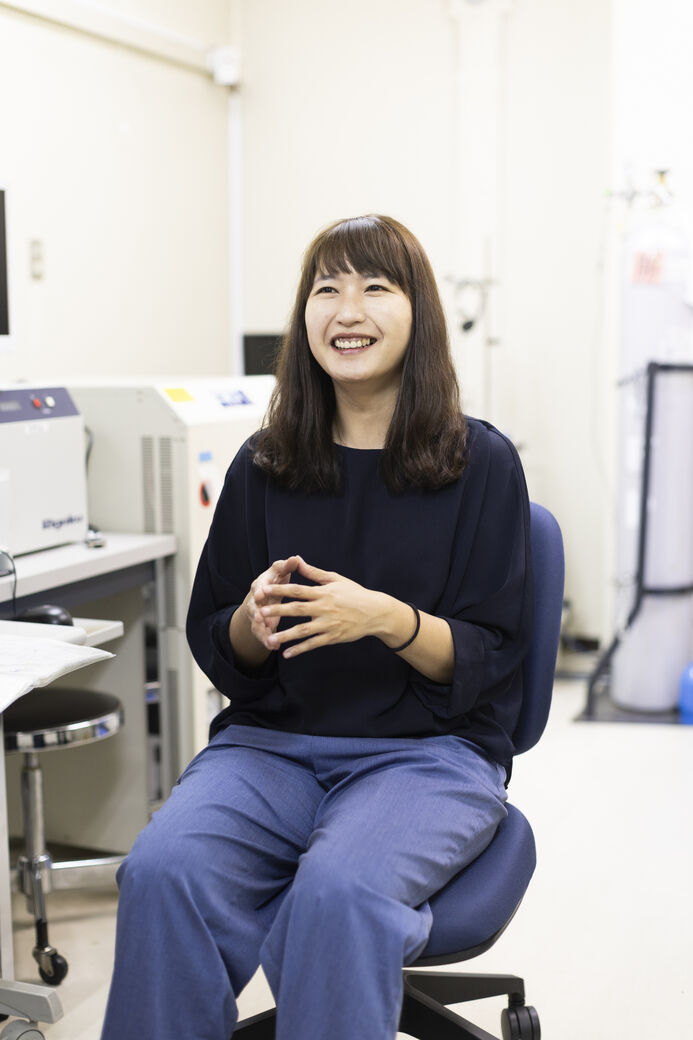捨てる前に、もう一度耳をすますーモノが語る再生の道 - 郭 妍伶

機械系 助教 郭 妍伶
Q. 研究の中心はどこにありますか?
私たちは、製造過程で生じる産業廃棄物を「もういらないもの」ではなく、「新たな役割を持つ素材」として見直し、資源をやさしく使い続けるための研究に取り組んでいます。限られた資源をできるだけ長く使い、地域や未来にもやさしいものづくりを目指し、循環型経済のあり方を探っています。なかでも、材料の長寿命化はライフサイクル全体における環境負荷の低減やリサイクル頻度の削減、新たな資源使用の抑制につながる重要な技術です。
Q. どのようなアプローチを取っていますか?
高温でも性能を保てる合金やセラミックスを対象に、表面を保護する処理や自己修復機能を付与することで、材料を長く使える工夫を重ねています。また、リサイクル材料に含まれる意図しない微量元素、(たとえばNbやAlなど)が混ざることがありますが、そうした「ちょっとした混ざりもの」も、上手に活かしてあげることで、かえって材料を守る強さにつながることがわかってきました。例えば、耐熱合金にNbを含むと、表面にCrNbO₄という保護膜が形成され、酸素の侵入を防いでくれます。さらにAlを加えることで、この保護膜はより早く、安定して生成されるようになります。最近の研究では、CrNbO₄が酸素分圧に応じて欠陥構造を変化させ、内部から材料を保護する働きがあることが明らかになってきました。こうした仕組みの解明は、高機能リサイクル材料の開発に役立つと期待されています。
Q. 廃棄物はどのように再活用されていますか?
産業副産物の再資源化も、私たちの研究の柱の一つです。例えば、アルミニウム部品の製造過程で発生する「二次ドロス」は、これまで埋立処分に廃棄されてきましたが、このドロスを適切な温度で焼成・焼結することで、耐火断熱レンガや構造用材料としての再利用が可能です。このように、廃棄物が高機能材料として生まれ変わる実例が得られています。現在は主にアルミ副産物を対象としていますが、今後は鉄鋼業や機械加工業から出るスラグ、スケールなど、さまざまな分野の副産物にも目を向け、地域の資源循環と環境負荷低減に貢献する技術として発展させていきたいと考えています。
Q. この研究の魅力は?
「どう作るか」だけではなく、「どう使い切るか」まで考える材料設計にあると思います。技術だけでなく、人や地域、環境とのつながりを感じながら、少し先の未来にやさしく届くような研究でありたいと願っています。


郭 妍伶 Kuo Yen-Ling
機械系 助教(2025年7月現在)
- 2021年4月 - 現在 長岡技術科学大学 機械系 助教
- 2023年6月 - 2024年3月 国立ユーリッヒ総合研究機構(ドイツ) 客員研究員
- 2018年8月 - 2021年3月 北海道大学 大学院工学研究院 材料科学部門 研究員