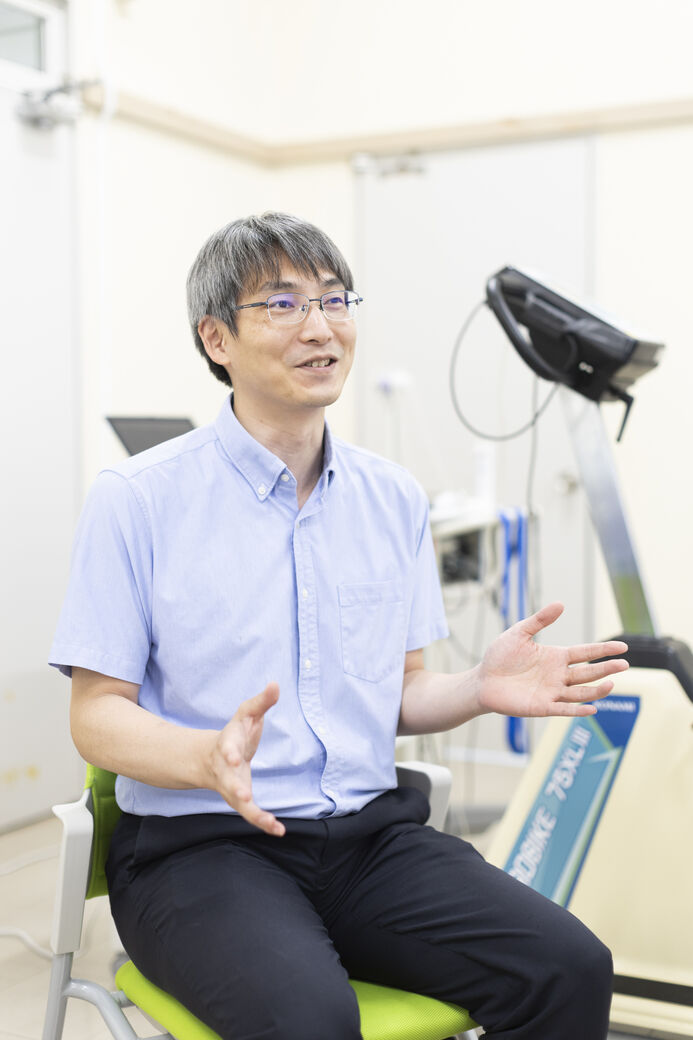運動中における活動筋の呼吸・循環機能を理解し、健康とスポーツを支援する - 奥島 大
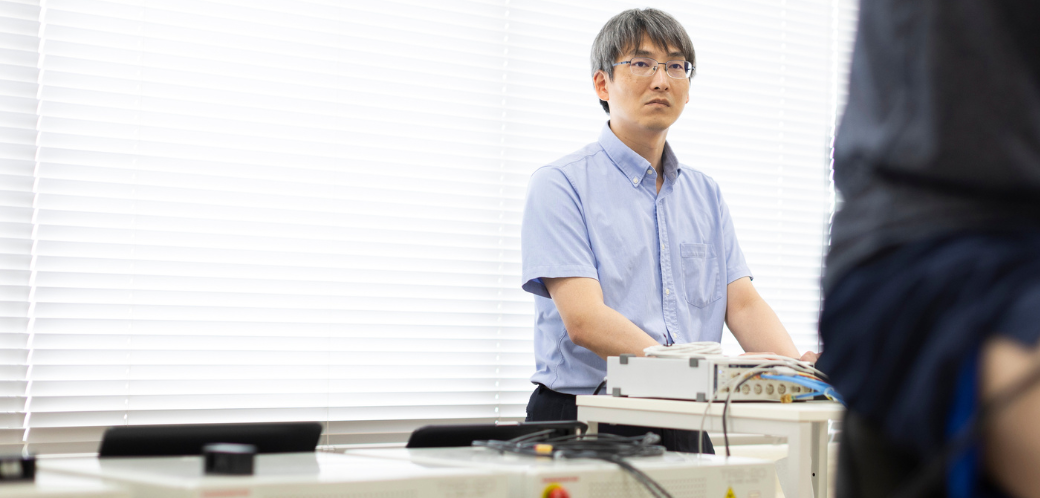
情報・経営システム系 准教授 奥島 大
Q. 研究の概要について教えてください。
人は運動・スポーツを行うとき、呼吸機能・循環機能・代謝機能など身体の様々な機能を連動させています。中でも、呼吸機能や循環機能の調節は興味深く、例えば身体各部に送り届ける血流量は、運動中に多くの酸素を必要とする筋肉(活動筋)や皮膚に全体の8~9割が分配されます。しかし、この活動筋や皮膚への血流分配は、単に酸素が必要かどうかだけでなく、身体の他の機能と調和を図りながら制御されているようです。そのため、運動中でも筋肉への酸素供給と酸素利用は活動筋の間で空間的に不均一に調節されていますが、その仕 組みはまだ完 全には解 明されていません。私たちの研究室では、運動中に生じる活動筋間の不均一な酸素調節の仕組みを解明し、スポーツや健康増進への応用を目指して研究を進めています。
Q. どのような方法で研究しているのでしょうか?
現在は、主に近赤外線分光装置といった、近赤外波長の光を生体組織に当て、返ってきた光の強さを測定することで、測定部位の血液量や酸素化状態(酸素量)を評価する機器を活用しています。一般的には、皮膚から1.5cm程度の深さまでの組織の情報を取得可能ですが、研究室には皮膚から3cm程度の深さまでの組織の情報を取得可能な機器も備えています。他にも、全身の酸素利用量を測定する呼吸代謝装置や、組織・血管の形状や血流量を測定する超音波画像診断装置なども活用しています。最近では、より詳細に活動筋の酸素利用と酸素供給の調節を評価することを目指して、近赤外光の拡散の度合いから赤血球の移動速度を測定する拡散相関分光装置の活用にも取り組んでいます。
Q. 運動中における酸素の供給と利用の調節メカニズムを理解することで、どのような応用が期待されますか?
例えば、持久力の高い人や低い人の特徴であったり、長期的なトレーニングによる変化の特性を理解することで、運動能力やトレーニング状況の評価に応用できます。また、加齢や疾患にともなう身体機能の低下との関連性について理解することで、健康状態の評価やリハビリテーション状況の把握といった健康増進分野に応用することも可能です。近赤外線分光装置はウェアラブルな機器も開発されつつあり、研究で得られた知見を広く応用することが期待できます。


奥島 大 Okushima Dai
情報・経営システム系 准教授(2025年7月現在)
- 2025年4月 - 現在 長岡崇徳大学 看護学部看護学科 非常勤講師
- 2024年4月 - 現在 長岡技術科学大学 情報・経営システム系 准教授
- 2019年4月 - 2024年3月 大阪国際大学 人間科学部 スポーツ行動学科 講師
- 2015年4月 - 2024年3月 大阪工業大学 工学部 非常勤講師
- 2021年10月 - 2022年3月 鹿屋体育大学 体育学部 スポーツ総合課程 非常勤講師
- 2017年4月 - 2019年3月 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(PD)
- 2013年10月 - 2017年3月 神戸芸術工科大学 芸術工学研究所 研究員