数理・データサイエンス教育研究センター
更新日:2023年10月2日
設置目的
実践的な数理・データサイエンス教育の全学的展開とeラーニングによる全国の高等専門学校等への展開を推進することを目的としています。
概要
基礎的な数理・データサイエンス教育の全学的な実施とFD活動等を通じた他の国公私立の大学(地域の大学、学部構成が共通する大学等)への数理・データサイエンス教育の普及の促進を目指しています。
業務内容
- 数理・データサイエンスに係る教育及び研究を行います。
- 数理・データサイエンスに係る教育プログラム等の開発及び支援を行います。
- 数理・データサイエンスに係る情報発信を行います。
- 全国的な数理・データサイエンス教育の推進に係る他大学等との連携業務を行います。
長岡技術科学大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本学では、情報技術を活用した技学教育によって、日本が現時点で強みを持つ「ものづくり」を数理・データサイエンス・AIを活用してそのプロセスを革新し、産業競争力を高めることができる人材を輩出することを目指しています。
このため、数理・データサイエンス・AIの知識・技能を専門分野に関わらず学生が修得できるような教育プログラムとし、産業界や自治体と連携して高水準で実践的な内容の数理・データサイエンス・AI教育プログラムを構築し、より高水準な教育内容への充実を図っています。
![]() 数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム【概要】(PDF:517KB)
数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム【概要】(PDF:517KB)
![]() 数理・データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム【概要】(PDF:339KB)
数理・データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム【概要】(PDF:339KB)
文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の認定
リテラシーレベルの認定

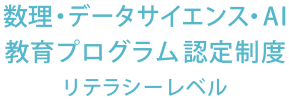
本学は、令和4年8月24日付け4文科高第681号により、文部科学大臣から実施する教育プログラムに対し、下記のとおり認定されました。
記
- 教育プログラム名: 数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム
- 認定の認定結果:認定
- 認定の有効期限:令和9年3月31日まで
- 特記事項
(1)実施要項第4条により、認定されたプログラムを変更又は廃止をした場合は、すみやかにその旨を文部科学大臣に届け出ること。
参考1.
![]() 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)申請書(PDF:2,215KB)
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)申請書(PDF:2,215KB)
参考2.
![]() リテラシーレベルロゴマーク(Word:230KB)
リテラシーレベルロゴマーク(Word:230KB)
※認定又は選定された教育プログラムを対外的に発信する際に使用可能です。使用にあたっては認定期限を明記してください。
応用基礎レベル(大学等単位)の認定

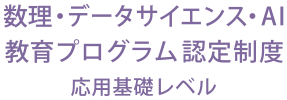
本学は、令和5年8月25日付け5文科高第753号により、文部科学大臣から実施する教育プログラムに対し、下記のとおり認定されました。
記
- 教育プログラム名:数理・データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム
- 認定結果:認定
- 認定の有効期限: 令和10年3月31日まで
- 特記事項
実施要綱第4条により、認定されたプログラムを変更又は廃止をした場合は、すみやかにその旨を文部科学大臣に届け出ること。
参考1.![]() 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)申請書(PDF:248KB)
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)申請書(PDF:248KB)
参考2.![]() 応用基礎レベル(大学等単位)ロゴマーク(Word:210KB)
応用基礎レベル(大学等単位)ロゴマーク(Word:210KB)
※認定又は選定された教育プログラムを対外的に発信する際に使用可能です。使用にあたっては認定期限を明記すること。
自己点検
数理・データサイエンス・AI教育プログラムを改善・進化させるための分析・検証については本センターで実施し、プログラムを構成する授業科目については、教育方法開発センターで実施している授業アンケートにより各科目の点検を行っています。
本学の授業アンケートは、学生が授業や教員を評価する目的ではなく、学生自身の期待と授業の内容や教え方とがマッチしているか、その授業が理解できて自身の能力が向上したか等の設問から成り、また、自由記述欄も設けており、学生と教員とのコミュニケーションのためのツールと位置付けています。
この授業アンケートの結果に基づいて、教員はよりわかりやすい授業のための工夫を考え、教員アンケートとして大学に提出するようになっており、よりわかりやすい授業のための工夫が継続的に行われると期待できます。
教育方法開発センターのホームページは![]() こちら
こちら
大学の自己点検・評価等についてはこちら
数理・データサイエンスAI教育プログラム自己点検・評価
担当教員(兼務)
| 教授(センター長) | 岩橋 政宏 |
|---|---|
| 教授(副センター長) | 坪根 正 |
| 教授 | 倉橋 貴彦 |
| 教授 | 湯川 高志 |
| 教授 | 野村 収作 |
| 准教授 | 木村 悟隆 |
| 准教授 | 松田 曜子 |
| 准教授 | 山崎 渉 |
| 教授 | 原 信一郎 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
学務課
